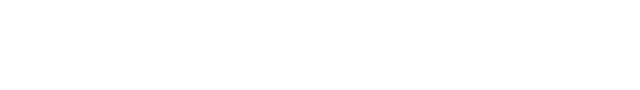梅毒激増の真実を泌尿器科専⾨医が解説
〜性感染症の脅威〜
はじめに
皆様は「梅毒」と聞いてどんなことを想像しますか?
「不治の病」「命に関わる病気」など、罹患すると恐ろしいというイメージをお持ちではないでしょうか。その証拠に実際に患者様の診療をしていても、梅毒感染を告げると絶望する⽅が多いのが現状です。
ここで、おそらく⽇本で⼀番多く、梅毒患者様を診療してきたであろう私が声を
⼤にしてお伝えさせていただきます。
「梅毒は抗⽣物質であっさり治ります」
1 梅毒とは
梅毒とは梅毒トレポネーマという『細菌』が引き起こす性感染症です。主に性交渉を通じて感染しますが、⾎液を介して感染するケースや⺟⼦間で感染するケースもあります。
梅毒は感染からの経過に応じて第1期から第4期に分類されます。
| 第1期 |
|
|---|---|
| 第2期 |
|
| 第3期 |
|
| 第4期 |
|
第2期までに医療機関を受診される⽅がほとんどであり、第3期・第4期の患者様は稀となっています。
梅毒の第2期
2 梅毒は怖い?
梅毒トレポネーマ、バラ診、ゴム腫などと聞くと「梅毒はやっぱり怖いのではないか」と感じる⽅もいるかもしれませんね。
しかし記事のはじめにお伝えさせていただいたように、梅毒トレポネーマは『細菌』の⼀種です。細菌とは微⽣物の⼀種であり、分かっているだけでも100 万種以上の様々な種類が存在するとされています。
では『細菌』に感染した場合の治療はどうすれば良いのでしょうか。
細菌の治療は抗⽣物質を使って細菌の活動を抑制または殺菌するという治療法が確⽴されています。
梅毒の場合には「ペニシリン」という抗⽣物質が⾮常に効果的であり、治癒率はほぼ100%に近いとされています。ペニシリンは梅毒の原因菌であるトレポネーマに対して強⼒な殺菌作⽤を持っており、適切な治療を受けることで梅毒を完治させることができます。さらに進⾏した第3期梅毒では治療に時間がかかることもありますが、それでもペニシリンによる治癒効果は⾼い確率となっています。
つまり、梅毒はあっさり完治が可能な疾患なのです。
3 マスコミの過剰な反応
2024年の⽇本の梅毒患者数は14663⼈と発表されました。この数字は感染症発⽣動向調査の全数把握感染症に定められた1999年以降最多となっており、これについてマスコミでは恐怖を煽るような形で報道されました。
遡ること江⼾時代には遊郭(性⾵俗を提供する場所)が登場、特に都市部で繁盛し、梅毒が爆発的に流⾏しました。江⼾時代にはペニシリンがなかったため、梅毒で多くの⽅が亡くなるという悲惨な状況となってしまいました。
第3期・第4期の症状である⿐が崩れる、ゴム種などの⾒た⽬のインパクトも強く、「梅毒は怖い」「梅毒にかかったら終わり」というイメージが現在も未だに残っていることは紛れもない事実だと思われます。
マスコミは梅毒について、ペニシリンで完治が可能であること、現在では梅毒で亡くなる⽅はほとんどいないことなどの情報を正しく伝えていただいているでしょうか。答えは否ではないかと考えます。
正しい情報を伝えていただいた上で、不特定の⼈との性⾏為をしない事や、正しいコンドームの使⽤を勧める報道をしていただきたいと願います。
4 梅毒の診察の流れ
我々のクリニックは⼤宮・上野・池袋・新橋にあるため、⼟地柄、梅毒の患者様が多くいらっしゃいます。皆さん⼝を揃えておっしゃるのが医療機関を受診することへの不安や抵抗感です。
「何をされるんだろう」「治療⽅法は?」「何回通院するんだろう」など先が分からないからこそ起こる不安によって受診を躊躇している⽅が思いのほか多いのが現状のようです。
そこで、診察→検査→治療の⼀般的な流れを簡単に説明させていただきます。これをご覧になり、不安の軽減に少しでも繋がると嬉しいです。
4-1 診察
感染の機会はあったか、またはいつ頃か、どのような症状があるかなどの問診を⾏います。
合わせて、感染部分の潰瘍やしこりの有無、バラ疹の有無などを確認するため、視診や触診を⾏うこともあります。
4-2 検査
梅毒の検査は⾎液検査です。採⾎をして梅毒に感染していると検出される抗体(RPR・TPHA)が検出されるかを調べます。
4-3 治療
| ①内服の場合 | ペニシリンを1ヶ⽉間毎⽇内服 |
|---|---|
| ②注射の場合 | ペニシリンの注射薬を筋⾁注射で1回 (第3.4期梅毒の場合、週に1回を計3回) |
4-4 治癒の確認
1ヶ⽉間の内服治療が終了、または注射による単回治療が終了した後は、4週ごとに採⾎をしてRPR値を確認していきます。RPR値が最⼤値の半分以下まで減少して、その後の上昇がなければ治癒と判定します。そのため、経過が順調でも3ヶ⽉後、6ヶ⽉後に再検査をするのが⼀般的です。
5 意外と多いペニシリンアレルギー
ペニシリンアレルギーをお持ちの⽅の割合は⾮常に⾼く、⼀般的には⼈⼝の約5〜10%と⾔われています。ペニシリンアレルギーの症状は⼈によって様々で、⽪膚に発疹や蕁⿇疹ができる⽅もいれば、重症例の場合、呼吸困難やアナフィラキシーショックを起こす⽅もいらっしゃるくらいです。
そんなペニシリンアレルギーの⽅に対しては抗⽣剤のミノマイシンが有効であり、その効果はペニシリンと同等であるという報告があります。
6 守りたい命のために
梅毒に感染しないためには梅毒に関する正しい知識を持つことと、感染予防対策(安全な性⾏為、コンドームの使⽤)が何より⼤切です。
これらは⾃らが意識して⾏動できることであり、特に妊娠や出産の適齢期の⼥性やそのパートナーは⼗分に注意することが必要です。
梅毒に感染したまま⼥性が妊娠し、適切な治療を受けていない場合、胎児にも感染してしまう確率が⾼くなります。「先天梅毒」の⾚ちゃんは⽔疱や丘疹などの⽪膚症状、リンパ節腫脹、肝脾腫、⾓膜炎、難聴などのリスクが伴います。
2023年の⽇本の先天梅毒は37例となっており、こちらも感染症発⽣動向調査の全数把握感染症に定められた1999年以降最多となりました。
梅毒は早期に治療すれば完治が可能であり、過度に恐れる疾患ではありませんが、これから⽣まれてくる命は守られるべきだと思います。
7 ブライダルチェックの有⽤性
梅毒だけではなく、淋菌やクラミジアなどの性病にかかる⽅が近年急増していることに⾏政などは警鐘を鳴らしてはいますが、実際の患者数はそれをかき消してしまうほどに多くなっています。
誰でも性病に感染してしまう恐れがある現代、ブライダルチェックなどを定期的に受けて現在の状況を把握しておくことが⼤切なのではないでしょうか。男⼥ペアで受けると助成⾦の対象となる都道府県もありますので、お住まいの市区町村に問い合わせて⾒るとよいでしょう。
また、「ブライダルチェック」という名称により、結婚の予定がないと受けられないと誤解している⽅も多いようですが、性病が⼼配な⽅が1⼈でも受けられる医療機関も多くなっています。(この場合は助成⾦対象外です。)
8 まとめ
梅毒患者数は急増しており、危惧する状況であることには変わりありません。
しかしマスコミの情報に流されず、過度に恐れず、偏⾒を持たず、治療法が確⽴された完治が可能な疾患だということを覚えておいてください。
誰よりも梅毒患者様の診療をしている私の臨床経験から「梅毒はただの感染症、⾵邪のようなもの」と思うのです。
日本泌尿器科学会認定・泌尿器科専門医
名古屋大学出身
年間30000人以上の泌尿器科と消化器科の外来診察を行う
YouTubeでわかりやすい病気の解説も行なっている。