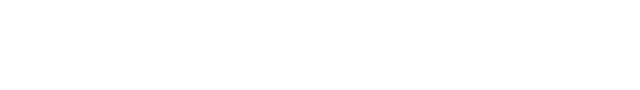癌(がん)の発症リスクを⾼める「最悪の⽣活習慣10 選」
はじめに
⽇本では⽣涯で2⼈に1⼈が癌を経験し、3⼈に1⼈が癌で命を落とすと⾔われています。平均寿命が伸びた現代、「⻑く⽣きる=細胞が傷つく時間も⻑い」ため、癌はさらに⾝近な疾患となっています。
しかし、その中でも希望もあります。厚⽣労働省の統計では、癌死亡の約40%が⽣活習慣を改善することで予防できるとされているのです。つまり⽇々の選択や習慣が、未来の健康を左右するということに繋がります。
ここでは、実際に診療現場で繰り返し⽬にしている「癌を招いてしまう⽣活習慣10選」をご紹介させていただきます。それぞれのリスクと対策を知った上で、正しい選択をしていきましょう。
癌の発症リスクを⾼める習慣その① 喫煙
タバコに含まれる70種類以上の有害物質は、喉頭がん・肺がん・⾷道がん・膀胱がんなど複数の癌と深く関係しています。世界保健機関(WHO)の外部機関であるIARC(国際がん研究機関)は、喫煙を「発がん性が明らかである」 とされるグループ1に分類しています。特に喫煙者は⾮喫煙者に⽐べ、肺がんのリスクが数倍⾼くなると⾔われているのはみなさんもご存知の事と思います。
禁煙はがん予防における最も効果的な⼿段です。近年では禁煙外来を利⽤し、医師のサポートのもとで禁煙補助薬やニコチン代替療法を取り⼊れることで、成功率が格段に上がっています。喫煙習慣がある⽅は、まず相談から始めてみましょう。
「喫煙は100害あって⼀利なし」です。
癌の発症リスクを⾼める習慣その② 飲酒
アルコールは発がん性物質に分類されており、少量であっても継続的な摂取は肝がん・⾷道がん・乳がん・⼤腸がんなどのリスクを⾼めます。アルコールは喫煙と同じく「発がん性が明らかである」とされるグループ1に分類されており、ビール中瓶3本程度のアルコールを毎⽇摂ると、癌のリスクが約40%も上がるという報告もあります。
そのため、習慣的に飲酒をされている⽅はその習慣を⾒直すことが重要です。週に数⽇の休肝⽇を作る、ノンアルコール飲料を取り⼊れる、お酒の量や頻度を記録するなど、⾃分に合った⼯夫で無理なく減酒を進めていくことが⼤切です。
癌の発症リスクを⾼める習慣その③ 肥満
肥満は⼤腸がん・膵臓がん・乳がん・⼦宮体がんなど複数の癌に関係しています。特に内臓脂肪は慢性的な炎症を引き起こし、免疫を低下させ、癌が発⽣する絶好の⼟台となってしまいます。そのため、適正範囲を⼤きく超えた体重は減量をして適正範囲内に戻しておくことが癌の予防に直結します。
当院では、GIP/GLP-1受容体作動薬(マンジャロ、オゼンピック、リベルサス)を使⽤したメディカルダイエットを提供しています。これらの薬は、⾎糖コントロールを改善するだけでなく、⾃然な⾷欲抑制と代謝促進効果をもたらします。医師の管理のもとで使⽤することで、無理なく健康的に体重減少を⽬指すことが可能となり、現在では多くの⽅がメディカルダイエットを選択しています。当院スタッフや医師も使用しており、⽣活習慣の改善と組み合わせて取り組むことで、癌だけでなく糖尿病などの⽣活習慣病予防にも繋がります。
癌の発症リスクを⾼める習慣その④ 運動不⾜
運動不⾜は肥満だけでなく、癌そのもののリスクも⾼めます。軽い運動でも⾎流が改善され、免疫機能が⾼まり、癌の予防に繋がるのです。
まずは、毎⽇の⽣活の中で少しずつ⾝体を動かすことが⼤切です。通勤時に⼀駅分歩く、エレベーターではなく階段を使う、テレビを⾒ながらストレッチをするなど、⼩さな習慣が積み重なれば、⼤きな健康効果を⽣む事となります。週に150分(1⽇30分×5⽇)の有酸素運動を⽬安に、無理なくできる範囲で取り組みましょう。
癌の発症リスクを⾼める習慣⑤ 塩分の摂りすぎ
塩分の過剰摂取は、胃の粘膜を傷つけて胃がんのリスクを⾼める要因になります。ラーメンや漬物、加⼯⾷品などは認知されていますが、パンやチーズ、ドレッシング、カップスープなど⼀⾒塩分が多そうに⾒えない⾷品にも意外と多くの塩分が含まれていることがあります。外⾷やコンビニ⾷品が多い⽅は、知らず知らずのうちに1⽇の推奨量を⼤きく上回っている恐れもあるのです。
⽇々の⾷事で塩分を減らすには、だしや⾹⾟料を活⽤して⾵味を出す、調理中に味付けを控えめにして⾷卓で調整するなどの⽅法があります。また、栄養成分表⽰を確認し、1⽇の塩分摂取量を意識する習慣をつけることも効果的で す。「塩分⾒える化」というわけですね。
癌の発症リスクを⾼める習慣その⑥ 野菜・果物不⾜
⾷物繊維や抗酸化物質が不⾜すると、腸内環境が悪化し、発がん性物質の解毒能⼒が落ちてしまうと⾔われており、特に⾷道がんや胃がんのリスクが⾼まる傾向があります。
そこで忙しい⽇常の中でも、野菜や果物を積極的に摂る⼯夫が⼤切です。⽣サラダだけでなく、野菜炒め、野菜スープ、スムージーなど、調理法を⼯夫すれば⼿軽に野菜が多く摂取できます。1⽇400g(両⼿⼭盛り)を⽬安に、継続していくことが重要です。
また、果物にはビタミンやポリフェノールなど抗酸化作⽤のある栄養素が豊富に含まれているため、積極的に取り入れたいものです。
野菜と果物はどちらも⼤切ですが、果物は果糖が多く含まれており、過剰摂取は⾎糖値や内臓脂肪に影響を与えることがあるので摂りすぎに注意しつつ、あくまでバランスよく取り⼊れることを意識しましょう。
癌の発症リスクを⾼める習慣その⑦ 加⼯⾁・⾚⾝⾁の過剰摂取
ハム・ソーセージ・ベーコンなどの加⼯⾁、また⾚⾝⾁を多く摂ることは、⼤腸がんのリスクを上昇させるといわれています。特に加⼯⾁は国際的にも発がん性が明確に⽰されています。加⼯⾁はタバコと同列の「グループ1(発がん性あり)」に分類しています。最近ではそのリスクも広く知られるようになってきましたが、それでもスーパーなどで⼿軽に購⼊できるという現実には注意が必要です。お⼦さんのお弁当などで使われることも多いため、⼤⼈だけでなく家族全体で意識して取り組むことが⼤切です。
⾷⽣活の中で、⾁類を減らすことは意外と簡単です。例えば週に2回は⿂中⼼のメニューにする、⼤⾖製品(⾖腐、納⾖、厚揚げ)を取り⼊れる、⾁を使う場合は量を減らし野菜を増やすといった⼯夫が健康的な⾷⽣活につながります。また、購⼊する際には亜硝酸塩や発⾊剤を極⼒含まない「無添加」や「無塩せき」と表⽰された商品を選ぶよう⼼掛けることで、発がん性物質の摂取をさらに抑えられます。
癌の発症リスクを⾼める習慣その⑧ 熱すぎる飲⾷物
70℃以上の熱い飲み物は、⾷道の粘膜を傷つけ、繰り返されることで知らず知らずのうちに⾷道がんのリスクを⾼めると⾔われています。
熱すぎる飲み物や汁物を⼝にする際は、少し冷ましてから飲むようにしましょう。注いでから5分ほど置く、氷や冷⽔を少量加えるといった⼯夫をすることで、⼝腔や⾷道への負担を軽減できます。
癌の発症リスクを⾼める習慣その⑨ 質の悪い睡眠
短い睡眠時間や不規則な睡眠は、免疫の働きを低下させ、乳がんや前⽴腺がんのリスクを⾼めることが分かっています。
良質な睡眠を得るためには、まず睡眠環境を整えることが重要です。寝室の明かりを落とし、静かな空間で寝る、寝る前のスマートフォンやカフェイン摂取を控えるなど、眠りに⼊りやすい習慣を作っていきましょう。⼗分な睡眠は、がん予防だけでなく、⾝体の修復と免疫⼒の回復に直結し、さらに⽇中の気分を安定させて活⼒をもたらすことも知られています。
癌の発症リスクを⾼める習慣その⑩ 痩せすぎ
「痩せ=健康」とは限りません。極端に痩せた体は免疫⼒が低下し、癌の発症リスクも⾼まる傾向にあります。痩せていることが美しいという価値観に偏りすぎると、健康を損なってしまう可能性があります。特にBMIが18未満の⽅は注意が必要です。
無理なダイエットではなく、栄養バランスの取れた⾷事と適度な運動を継続することで、⾃然と健康的な体型が維持されます。体重を気にするあまり栄養が不⾜してしまわないよう、医師のアドバイスを受けながら、健康的に栄養バランスを整えて取り組むのが安⼼ですね。
まとめ
癌は「運」や「体質」だけではありません。⽣活習慣を整えることで、そのリスクを⼤きく下げることが可能です。今回紹介した10の⽣活習慣に⼼当たりがある⽅はぜひ⾒直していただき、できることから改善することで、癌の予防効果は確実に⾼まります。まずは意識して⾏動する「初めの⼀歩」から!
新橋消化器内科・泌尿器科クリニックでは消化器、泌尿器、内科を中⼼とした幅広い診療をおこなっております。メディカルダイエット、消化器ドック(胃カメラ・⼤腸カメラ・CT)もおこなっており、⽣活習慣改善から疾患の早期発⾒・早期治療まで幅広いサポートをしています。
今回の記事をご覧いただいたことで、「意識して⾏動する」きっかけとなると幸いです。
がん予防は、毎⽇の⼩さな選択の積み重ねです。
日本泌尿器科学会認定・泌尿器科専門医
名古屋大学出身
年間30000人以上の泌尿器科と消化器科の外来診察を行う
YouTubeでわかりやすい病気の解説も行なっている。