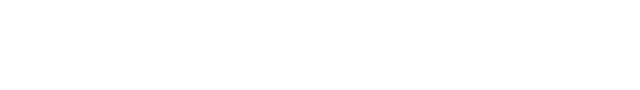胆石症の症状・原因・検査・治療について
胆石症と聞くとどのようなことを想像するでしょうか。
近年、食生活の欧米化に伴い、胆石症や胆嚢炎が増加傾向にあり、日本人の約10%弱が胆石を持っているという報告もあります。
胆石を持つ人の多くは無症状ですが、時に胆石発作や胆嚢炎を引き起こす可能性があり、注意が必要な疾患です。
この記事では胆嚢の働きや胆石症の症状・原因・検査・治療法について消化器内科専門医がわかりやすく解説しますので参考にしていただければ幸いです。
1 そもそも胆嚢とは何をするところか
胆嚢は、西洋梨のような形をしており、肝臓で作られた胆汁を貯めておく働きがあります。
胆汁は消化酵素の一種であり、食事を摂ると胆嚢に貯まった胆汁が胆管を通じて十二指腸に流れ出します。
2 胆石症とは
胆石症は、胆汁の成分が固まってできた結石が胆管や胆嚢に溜まる病気です。
結石のできる部位によって、最多の胆嚢結石の他に、総胆管結石、肝内結石があります。
超音波検査で確認できる胆嚢結石
胆石の主成分は7割以上がコレステロール結石と言われ、その他ビリルビン結石などがあります。
3 胆石症の現状
胆石症の患者数は、1990年代には日本で人口の約10%はに達したと言われてきました。
近年は食生活の欧米化と肥満者の増加から、胆石保有者は更に増加していることが予想されます。
4 胆石症の原因・リスク
胆石症の原因は全てが解明されていませんが、古くから40歳代、女性、肥満、白人、妊娠・出産が危険因子と考えられています。
その他には高カロリー食や極端なダイエット、脂質異常症もリスクであると言われています。
5 胆石症の症状について
超音波検査で確認できる胆石
胆石症は、無症状のことも多く、健診などで偶然に発見されるケースがほとんどですが、その中で3割程度の人は胆石症により下記のような症状が現れます。
5.1 胆石発作
胆石発作は、食後、特に油ものを多く含む食事を摂取後に右の肋骨の下部やみぞおちに強く痛みが現れます。
痛みが右肩まで広がることもあります(放散痛)。
5.2 発熱・寒気
胆石が胆嚢や胆管の出口を塞ぎ胆汁の流れが悪くなることで(うっ滞)、胆嚢や胆管に炎症が起き、感染を起こし、発熱や腹痛、寒気が出現することがあります(胆嚢炎、胆管炎)。
5.3 黄疸
黄疸は、白目や皮膚が黄色くなる症状です。胆石(胆管結石)によって胆汁の流れがせき止められてしまうと、胆汁が十二指腸に排泄されずに血液中に流れ、黄疸を引き起こします(閉塞性黄疸)。
黄疸には、皮膚のかゆみを伴うことも多く、また、紅茶やコーラの色のような尿が出ることもあります。
6 胆石症の検査について
6.1 血液検査
胆嚢炎や胆管炎など細菌感染を起こした場合には、白血球などの炎症反応の増加が認められます。
また胆石が胆管に落ちて胆管炎を発症した場合は、肝臓や胆道系の酵素の数値が上昇します。
6.2 腹部超音波検査・腹部CT検査
胆石があるか、胆嚢の腫れがあるか、胆嚢の壁が厚くなっていないか、胆汁うっ滞による胆管の拡張がないかなどを調べます。超音波検査とCT検査は胆石の診断にとても有効です。
CTで確認できる胆石
超音波検査で確認できる胆石
新橋消化器内科・泌尿器科クリニックでも超音波検査、CT検査を行っております。
6.3腹部MRI検査
MRCPはMRIを使用して胆嚢・胆管・膵管を同時に観察できる検査です。
MRIは放射線を使用しませんので、身体に負担のかからない検査です。
CTでは検出できない種類の結石も見つけることができる場合があります。
7 胆石症の治療について
痛みなどの症状がない場合には、血液検査や腹部超音波検査など定期的な検診を受け、経過観察で問題ありません。
しかし、発作が起きて腹痛や発熱など症状が現れた場合には、病状に応じて下記の治療を行います。
7.1 溶解療法
胆石の成分を溶かす作用がある内服薬を服用します。
痛みなどの自覚症状が軽度でコレステロール結石が疑われ、サイズが小さい場合には、薬を継続し経過観察を行うことがあります。
胆石が溶ける割合は2割程度で再発も多いと言われており、高い効果は期待できません。
7.2 体外衝撃波粉砕療法(ESWL)
体外より衝撃波を結石に向けて当て、粉砕して除去する方法です。
しかし小さくなった結石が落下するときに胆嚢炎や胆管炎、膵炎など重篤な合併症が起きるリスクがあり、また再発するケースも多く、再発率は1年で20%、5年で40%程度と言われているため、現在ではあまり行われておりません。
7.3 外科手術:胆嚢結石に対して
症状のある胆嚢結石に対しては手術が第一選択となります。
胆石の手術は胆石のみを除去しても再発することが多いため胆嚢ごと摘出します。
1990年代以降はお腹の傷口が小さく術後の痛みが少ない腹腔鏡下での胆嚢摘出術が広く行われています。
7.4 内視鏡治療:胆管結石に対して
胆管内の結石は放置しておくと胆管炎を生じるリスクがあるため、原則症状がなくても治療の必要があります。
治療は現在では内視鏡技術が進歩したため、内視鏡治療が一般的です。
胆汁が流れるように胆管にチューブステントを留置したり、出口を切開した後にバスケットやバルーン状のカテーテルなどで結石を除去したりします。
8 胆石症のリスク・予防について
8.1 肥満や脂質異常症
LDLコレステロールや中性脂肪が高い場合、胆汁内のコレステロールの濃度が上昇して胆石ができやすくなります。
肥満を避け、適正体重に近づけることが脂質異常症や生活習慣病の予防になり、胆石症、胆嚢炎の予防にも繋がります。
8.2 不規則な食生活
不規則な食生活で、食事と食事の間隔が空きすぎると胆汁が濃縮されて、結石ができやすくなります。
1日3食、できるだけ規則正しい時間に食べるようにしましょう。
8.3 脂肪分の多い食事
動物性脂肪や糖質の摂取量が多いと血液中の脂質が上がりやすくなります。
脂身が多い肉、ハム・ソーセージなどの加工肉、糖質は控えめにしましょう。
8.4 暴飲暴食
暴飲暴食をすると、それを消化しようと胆汁が多く放出され、胆嚢や胆管に負担がかかってしまいます。
食事はゆっくりとよく噛んで、腹八分目を心がけることが大切です。
8.5 アルコール
アルコールによって胆汁が濃縮され、胆石のリスクが高まります。
アルコールのとりすぎは中性脂肪の上昇にも繋がりますので、飲みすぎには注意し、適量を心がけましょう。
8.6 女性ホルモンの減少
女性ホルモンの低下により血中コレステロールが増加する傾向にあり、胆石ができやすくなります。
40~50歳代以降の女性は、脂質異常症や肥満に注意することが胆石症・胆嚢炎の予防に繋がります。
9 胆石症を放置すると
既にお話したように、胆嚢結石の大部分は無症状であり、症状がなければ経過観察で問題ありません。
胆嚢炎となった場合には、外科手術(胆嚢摘出術)が必要となる場合があります。
一方で肝臓から十二指腸に繋がる胆管に結石を認めた場合には、無症状であっても胆管炎のリスクがあることから内視鏡治療の適応とされています。
10 胆石症の患者様の経過
10.1 50歳女性
健康診断で行われた腹部超音波検査にて胆嚢結石を指摘され、当院を受診された。CT、腹部超音波検査を行い、胆嚢内に最大8mm大の複数の結石を認めた。
胆嚢炎を疑う所見を認めず、無症状であったため治療適応はないと判断して、1年後に腹部超音波検査でフォローの方針とした。
10.2 38歳女性
以前、他院で胆嚢結石を指摘されたことがあった。
今回腹痛、発熱、黄疸が出現したため、当院を受診された。
血液検査で黄疸、肝胆道系酵素(肝臓および胆道系の数値)の上昇を認めた。
CT検査を施行したところ、総胆管(肝臓から十二指腸に流れる胆汁の通り道の一部)に5mm大の結石を認め、胆管の拡張を伴っていた。
総胆管結石とそれによる胆管炎の診断となり、他院に紹介となった。
他院にて内視鏡治療(結石除去術)が行われ軽快した。
11 胆石症の症状かなと思ったら
発熱や腹痛(特に右肋骨の下からみぞおちにかけて)に気づかれた方は、必ず一度消化器内科を受診しましょう。
新橋消化器内科・泌尿器科クリニックでは、胆石症の適切な検査・診断が行えます。
治療が必要な場合は適切な病院へご紹介いたします。
詳しくは当院医師・スタッフまでお気軽にお尋ねください。
12 診療費用
当院は全て保険診療です。
初診の診療費用は薬代を除き、おおよそ下記のようになります。(3割負担)
| 尿検査のみ | 2000円前後 |
|---|---|
| エコー検査のみ | 2500円前後 |
| 採血+尿検査 | 3500円前後 |
| 採血+尿検査+エコー検査 | 5000円前後 |
| CT検査 | 5000円前後 |
| 尿流量動態検査 | 1500円 |
| 膀胱鏡検査 | 3000円 |
| 胃カメラ | 4000円前後 |
| 大腸カメラ | 5000円前後 |
※3割負担の場合
名古屋大学出身
消化器病学会専門医
消化器内視鏡学会専門医
内科認定医
肝臓、胆嚢、膵臓から胃カメラ、大腸カメラまで消化器疾患を中心に幅広く診療を行っている。